2020年11月25日の日本経済新聞「私の履歴書」に、元東大総長、三菱総研理事長小宮山宏氏がご自身の英語との格闘の経験を書かれていました。
とにかく英語には苦労した。助手のころに1年間、米国に留学したとはいえ、それだけで「聞く」と「話す」が身につくものでもない。
研究者として初めて必要性に迫られたのが、大学院の博士課程最後の年だった。京都・宝ケ池にある国際会議場で1972年秋に開催された第1回PACHEC(太平洋化学工学会議)で、研究成果の発表をすることになった。
慌てて化学工学科の仲間4人と英会話の先生を雇うことにした。いわゆるグループレッスンである。米国人の先生からは「東大の若い研究者はこんなにも英語ができないのか」とあきれられた。英語の学校教育をまじめに受けてきたのに不愉快だが仕方ない。
それから三十数年後、まさか東大の総長室で英語の個人授業を受けるはめになるとは思いもしなかった。
専門の化学工学や地球環境問題がテーマであれば、内容もおおむね理解できブロークンな英語で話すことも問題ない。が、いかんせん、総長という立場だと政治や経済などのテーマで会話する機会が増える。周囲の人たちがみかねて、ベルリッツの個人レッスンを手配してくれた。
週1回、総長室で2時間ほど授業を受けるのだが、考えていたのとはまったく違った。新聞記事を読みながら時事問題について意見を交わしたかったが、発音の練習ばかり。日本人が苦手な「r」と「l」の区別をしなさいと言われるが、いまさら無理だ。
頭にきて先生を代えてもらった。すると次も発音にこだわる。「ウルトラ」を巡って口論となった。私が「発音記号通りに発音している」と辞書を示すと、「発音記号なんて知らない」と返してくる。
ベルリッツによると「あれ以上優秀な教師はいない」。結局、契約を解消した。その後は英字紙「ジャパン・タイムズ」を毎日読むようにし、知らない単語が出てくるたび辞書で調べ、単語帳に書き留め覚えるように努めた。
当時、東大の教養学部では英語の授業を見直していた。若いネーティブを20人雇いたいという。総長裁量経費で認めた。20人のうち半数は理系の人にしてもらい「サイエンティフィック・ライティング」という授業を導入した。自ら書くことで思考力も身につく。これを小人数で教養課程の必須にした。
こんな私だが工学部教授のとき、学生たちに英語を教えたことがある。同じ化学工学の後輩である斎藤恭一先生が中心になって始めた、その名も「理系のためのサバイバル英語」。駒場の一番大きい、数百人が入る教室がいつも満員になる超人気講義だった。この内容はのちにブルーバックスで本にもなった。
2008年夏、北海道洞爺湖でのG8サミットに合わせて初の大学サミットが開催された。東大の教職員が中心となって企画、運営し、私が議長役を務めた。アジェンダ設定も日本側でしたから、会議は大して問題はない。厄介なのが食事をしながらのフリーディスカッションだった。
ただ、日本語での会議もそうだが、全部を理解するものでもない。「3割、わかればいい」と考える。
英語で講演したあとの質問で、何について聞いているかさえわかれば、それについて自分の意見を述べる。これこそ「サバイバル術」である。
地道な努力の継続に勝るものはないと、再認識しました!
お読みいただきありがとうございました!
よろしければランキング応援クリックをお願いします。
↓↓
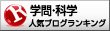
学問・科学ランキング
にほんブログ村
↓↓ツイッターをフォローいただくと、ブログ更新情報を受け取れて便利です。
Follow @tabbycat111


コメント
コメントを投稿